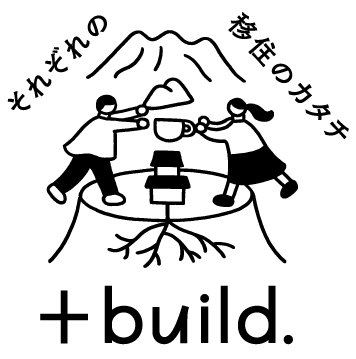INTERVIEW
新規就農の夢を叶えるため、福岡から移住
農業をはじめたいと移住を考える方も多いのではないでしょうか?個性豊かな地形ゆえの寒暖差や美しい水を育む、竹田市の基幹産業は農業です。稲作、野菜、牛豚鶏の飼育など多種多様な品目を生産する県内最大の食料生産地で、農業産出額も県内トップを誇ります。
今回は、新規就農の夢を叶えるために竹田に移住した夫妻をご紹介します。

祖母山麓にある、宮砥(みやど)地区。豊かな自然に恵まれた農村地域です。3人の子育てをしながら夫婦でピーマン栽培を営む、入江徹さんと妻の祐里子さん。竹田に移住して6年目を迎える夫妻に現在の暮らしについて伺いました。
- プロフィール
入江徹さん・祐里子さん
福岡県福岡市出身。徹さんは高校卒業後に就職するが、25歳の時に新規就農の夢を叶えるために農業へ転職。個人農家や農業法人で5年間勤務し、露地栽培や施設栽培を学ぶ。妻の祐里子さんは介護職に就いていたが、徹さんの夢を応援したいと夫婦で就農を決める。2020年に竹田に移住し、「竹田市ファーマーズスクール」に夫婦で入校し、2年間ピーマン栽培を学ぶ。2022年に修了後、新規就農者育成総合対策事業などの支援を受け、新規就農者として、現在はピーマンと白ネギ、水稲を栽培し、就農5年目を迎える。
-
移住するまでの経緯を教えてください。
徹さん:福岡でも農業をしており、農業法人に勤めていました。農業法人に勤めていた頃は、「何でも経験しておかないと」と多品目を栽培していました。5年が経過し、そろそろ独立したいなと考えていた時に福岡で大分県が主催する就農フェアをやっていて、竹田市のブースで今のピーマン栽培の師匠と出会ったんです。
祐里子さん:それまでにも他のブースにも行ったんですけど、だいたい市の職員の方が来ていて、農業のことを聞いてもデータ上の話しか聞けなかったんです。それに対して、竹田市のブースでは実際に農業経営している方が来ていて、具体的な数字やリアルな声が聞けたんです。去年の収益や地域性、こういう虫が出やすいとか。その場で聞きたかったことを直に答えてくれた。それが心に一番残ったんです。
 福岡に住んでいた頃の入江さん家族
福岡に住んでいた頃の入江さん家族徹さん:こちらも経験者ですから、詳しい内容を聞きたいのに実際に農業やってる人じゃないとわからない情報もある。自分は元々別の作物をやりたかったんですけど、農業初心者の妻と一緒にやるならピーマン栽培は比較的簡単だし、新規就農に向けたファーマーズスクールの制度もあるので竹田に来ませんか?と。その誘ってくれた方が後にファーマーズスクールのコーチになるんですけど、それがきっかけで移住することになりました。
-
移住に向けてどんな準備をされましたか?
祐里子さん:その就農フェアが2019年の夏で、翌年ファーマーズスクールに入校するための面接が10月にあって、面接を受けるまでが2ヶ月しかなかった。それまで竹田に行ったことがなくて、場所がわかってない(笑)。湯布院や別府はテレビで見たことあるけど、読み方も竹田(たけだ)でいいのかな?とか。
徹さん:申し込んだのはいいけれど、「竹田はどこかいな?」っていう。調べたら、結構な山の中で(笑)。久住は雪が降るらしいけど、雪が降るんかなあ?とか。
祐里子さん:大分だから暖かいかな?とか。実際に移住してみて、冬が寒いのにはびっくりしました。

竹田に移住後、家族でBBQ風景
祐里子さん:他の自治体も検討したけれど、ファーマーズスクールの開始時期が竹田は4月からで、それも決め手の一つでした。子どもたちの転校を考えると新学期が始まる時期が好ましかった。子育てする上では移動しやすいねって。
徹さん:夫婦で面接を受けて入校が決まり、2020年3月末に竹田に引っ越してきました。家探しは土地が全然分からないので、就農フェアでコーチと一緒に移住を勧めてくれた市の職員の方にサポートして貰いました。「幼稚園もここがいいよ」って教えてくださったり、地域の方々にも温かく迎えていただきました。
-
移住後の生活はいかがでしたか?
祐里子さん:移住した当時はちょうどコロナ禍が始まったばかりで、福岡の街から抜け出して来た感がありました。子どもが通っていた福岡の小学校ではソーシャルディスタンスが保たれ、人数制限しながらの登校など通学や行事もままならなかったようです。竹田では元々クラスの人数が少ないこともあって毎日変わらずの通学でした。普通に運動会もできましたし、行事がそこまで無くなることもなく、子どもたちは伸び伸びと過ごしていました。

子ども竹楽のイベントにて
徹さん:子どものためにも移住して良かったですね。楽しそうに学校に通っています。自然の行事が多いし、田植え体験とかね。川に行ったり、走るのも距離が長くて(笑)。福岡じゃ出来ないような体験ができていて良かったなと思います。
祐里子さん:小学校も中学校も朝は同じスクールバスで通っています。子育て支援の補助も福岡にいた時よりも手厚いです。息子たちは野球チームに入っていて、試合の応援に行くのも楽しみです。小学校の保護者も含めての懇親会もあったり、たまのそういう交流も楽しんでいます。

野球の試合でバッターボックスに立つ息子さん
祐里子さん:ピーマン栽培が始まると休みがなくなり、家族で出かけられることも少ないんですけど。引っ越した直後は家族全員が4月の入校まで休みだったので、皆で大分観光したんです。高崎山、うみたまご。阿蘇も近いからカドリードミニオン、豊後大野市の原尻の滝にも行ったのがいい思い出です。田舎に来ると、長距離運転には慣れてきますね。大分市まで1時間、熊本のコストコまで1時間半くらいかな。福岡にいる時は1時間の運転って、めちゃくちゃ遠く感じてたんです。こちらは渋滞も無いし、信号も少ないので運転しやすいですね。
-
都市部から移住して、不便だと感じた点はありますか?
祐里子さん:畑に近い地域に住んでいるので、家から買い物や病院までの距離が遠いですね。子どもが高熱の時に隣市の病院まで40分はかかるので、子どもが可哀そうって思いますし。もうちょっと家から店が近くて、飲食店とかあるといいなと思います。
徹さん:竹田はスーパーの弁当が半額になる時間帯が早いっていうのはいいです(笑)。福岡では値引きする時間帯も遅いし、半額までの値引きはなかった。お肉が半額になる時間に行って、売り場の前でずっと待っていたりします(笑)。
祐里子さん:こっちに来て、魚はあんまり食べなくなったかな。時々おいしい魚が食べたいなって思います。
徹さん:ゴマサバが食べたい(笑)。
-
就農から4年を経て、いかがでしたか?

4月中旬、ピーマンの苗を仕入れる
徹さん:ピーマン栽培は4月に定植して、収穫が6月から10月中旬までと約半年間です。畑の土地は借りていて、ビニールハウスは補助金を受けて自分たちで建てました。ファーマーズスクール修了後、最初の1年目はビニールハウスの建設が作付け時期に間に合わなくて、市の貸出し農園「スタートアップファームたけた」で始めました。2年目からは自分たちのハウスで栽培しています。

苗を定植し、栽培がはじまる
祐里子さん:ビニールハウスは温度管理が難しくて、天候や気温、水の管理、風通しを見ながら調節しています。特に夏は温度管理が大変で、心配でなかなか家に帰れないことも。以前に曇りだからと帰宅したら、陽が出てきてハウス内が高温になり葉が焼けてしまったこともあります。害虫の予防も難しく、その都度対応しています。
徹さん:今年の成長のメモを取っても、来年になったら気温も天候も何もかも違います。比較はできるけど参考程度にしかならない。土も衰えていたりもするし、伸び方も違う。去年うまくいったからといって、今年も同じようにいくとは限らない。毎年変わっていくし、そこは生き物、動物でも一緒。

5月初旬、最初に咲く「一番花」
祐里子さん:経営面でも、ピーマンの単価にはやっぱり波があります。コロナ禍で外食産業が休業していた時期は野菜が売れなくて値段が下がったり、毎年どうなるかわからない。
徹さん:全国的に豊作やったら値段も安くなるし、こんなに頑張っても台風でつぶれたりね。今のところ大きな被害はないけど、明日は我が身やけん。傍から見れば農業はのんびりしてるように見えるけど、本人たちは、もう必死こいてやりよる。

「一番花」を摘む、発育が良くなり沢山の実が収穫できる
祐里子さん:農業に転職して良かったのは、自分の好きなように時間を使えるようになったことです。以前の介護職は子どもの急な対応でも休みが取りづらくて、子どもが熱を出して仕事を休みたいと言っても、送迎や入浴介助の人が足りないからと休めなかった。福岡の病児保育サービスに子どもを預けて、1日2,000円位したんですけど。子どもを迎えに仕事を早めに上がると、給料が半分しかないじゃんっていう。休むとその日の給料は無い。パートだといくら頑張っても限界があるし。

祐里子さん:農業は栽培が始まると、その日から休みが無くなって、繁忙期は梱包作業で夜中まで働くこともあるんですが、その分売り上げが伸びる。子どもの体調が悪くても、家で子どもを看ながら収穫したピーマンのヘタも切れるし、その時間もお金になる。収入の変動はあるけれど、働いた分だけ給料が貰えるんです。
徹さん:儲かる所もあるけど、収穫するまでの間は完全にタダ働きになる。それに耐えられるかどうか。自分たちで計画を決めて時間は自由に使えるけれど、それなりの努力をしないといけない。

6月下旬、株が育ちピーマンが実りはじめる
祐里子さん:目標立てて、旅行に行きたいとか美味しいもの食べたいから、その分今を頑張るみたいな。ただ夏休みは収穫のピークで、家族で旅行に行くことはうちはできない。子どもたちは行きたそうだけど。ゴールデンウイークも定植で、毎日水やりで一番忙しいですし、シルバーウィークも収穫。行けるとしたら作業の合間をぬって、冬休みか春休みくらい。
-
これから新規就農する方へのアドバイスをお願いします。
 8月初旬、収穫のピークが訪れる
8月初旬、収穫のピークが訪れる徹さん:農業は良いこともたくさんあるし、新しい発見や面白いこともあるけど、何が起きるかわからないから、そのリスクも考えておかなきゃいけない。リスクが起きた時に乗り切る力がないと。何かあった時に周りの人に相談できるとか、自分が失敗しても他の人に助けてもらったり、仕事を紹介してもらったりとか、人付き合いも大事かな。
祐里子さん:どの職業よりも人と一番関わる仕事だと思う。ピーマン部会に所属することも必要で、個人出荷でなく共同出荷で価格が安定するくらいの量を出すので金額設定も話し合います。来年に向けて、こういう気候になりやすい、虫が出たらこうした方がいいとかの反省会もします。他の品目はどうですか?とかの情報共有もできる。60~70代の方も年齢関係なく若い私たちの言うことも聞いてくれて、「うちもやってみようかな」と勉強熱心な人が多い。ビニールハウスを張るのも1人じゃできないので、5人位で手伝い合いながらやっています。

10月まで収穫は続き、農協を通し西日本へ出荷される
祐里子さん:一人で農業をやるのは、なかなか大変だと思います。うちは夫婦で役割を決めて、農薬やトラクターの作業は夫が担当で、経理は私が担当しています。一人だったら、こういう作業も全部やらなきゃいけない。
徹さん:あまり神経質な人は向かないかもしれない。病気が出た時に、どうしようって逃げられなくなる。病気を出さないのが一番なんですけど、病気を出さないように真剣に薬をやっていたのに、出ちゃったら自分を追いつめちゃう。案外楽天的な方がいいかも。あとは、今年はこうだったから来年はこうしてみようとか、向上心や探求心のある人の方がいいと思う。

大きく立派に育った、収穫したピーマン
祐里子さん:移住に関しては、やってみないとわからない。やってみて初めて発見することがあるし、今まで知らなかった世界を知ることができます。もちろん大変なこともあるし、楽しいこともあるけど、そこは自分で道を開いていこう。やった分だけ、自分のものになります。
徹さん:農業をやりたいと思う気持ちはすごく大事です。でも理想と現実に差がある人ほど辞めていく人が多い気がしますね。農業はきついし、なかなか上手くいかない事も多いけど、その中にやりがいや楽しさが詰まっていると思います。天候にも左右されるから忍耐はいるし、何があっても最後までやり遂げなきゃいけない。そういう覚悟を持ってする仕事ではあります。
祐里子さん: それで一生やっていくっていう覚悟でいた方がいい。農業は試験や資格はいらないし、誰にでもなれる仕事だけど、誰にでも続けられる仕事ではない。1年や数年で辞められる仕事じゃないから。会社員は人間関係が嫌だからと辞めることができるけど、農業はそうはいかない。野菜も育っているし、辞めたくても辞められない(笑)。
徹さん: 収穫が始まると10月まで長いから、8月ぐらいで「もうピーマン終わらんかな~」って言い出すんですよ、毎年のように。もう疲れるから(笑)。そうは言うけど、収穫が終わりネット外して片付けをしてると「ああ、終わったね」って。でまた4月に定植すると、「もうキツイ!また始まったなあ」って。でまた8月になったら、「ああ、もう辞めてえな!」って(笑)。ずっと毎年それなんですよ。
―農業をいつまで続ける覚悟がありますか?
入江夫妻:動けるまで!(同時に)

-
- 編集後記
春から夏にかけて、入江さん夫妻を取材しました。定植を体験させいただいたのですが、手の体温で葉が弱ってしまうほど苗は繊細で、当たり前のようにスーパーに並ぶピーマンの栽培にここまで手間がかかるものだと初めて知りました。農業は一見スローライフのようにも見えますが、天候を見ながら分単位で作業工程を決め、黙々と忙しく作業されている姿が印象的でした。実が育ち始めるとビニールハウス内にピーマンの香りが漂います。灼熱の夏もどんな時も、成長を見守る夫妻の眼差しから、”ピーマンが可愛くて仕方がない”という気持ちが溢れていました。入江さん夫妻の想いと努力の結晶が、私たちの食卓に届きます。念願の生活を手に入れた入江さん家族の今後に期待です。
竹田市ファーマーズスクール
新規就農をめざす方のための研修制度。研修期間は2年間で、対象作物は「夏秋トマト」、「夏秋ミニトマト」、「夏秋ピーマン」。ベテラン農家を就農コーチとして付け、マンツーマンで営農の指導を行います。3年目には竹田市で就農する仕組みを構築しています。https://taketa-support.jp/about.php
スタートアップファームたけた
農業に挑戦したい方が、お試し感覚で農業を始められる場として大分県と竹田市が立ち上げた施設。農地と施設、機械などがセットで利用できます。